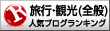前回から世界遺産検定についてご紹介してきました。そう、COVID19禍の中、旅行好きができるせめてもの抗い(あらがい)です。
前回は世界遺産検定とはどんな試験か?どんな問題が出題されるのか等を世界遺産検定1級を保有する私が解説しました。(マイスターについてはまた、後日お話します)
そんな世界遺産検定について、では具体的にどのような学習をすれば合格できるのかについてみていきましょう。
前回もご紹介したとおり、世界遺産検定の出題範囲(対象となる遺産数)は受験級別に異なってきますが、共通して言えることは、世界遺産についての総論と日本の世界遺産をしっかり理解しておけばほぼ合格したといっても過言ではありません。
それぐらい、特に総論は世界遺産についての知識を高める上でとても重要です。細かな世界各地の遺産は自身の興味に合わせて学習すればよいのです。
これは世界中に1,100件以上ある遺産個々の話ではなく、なぜ
世界遺産という概念ができたのか?どんな遺産が、どんな基準に基づいて
世界遺産に登録されるのか?
世界遺産に登録されるとどう言ったメリット、デメリットもあるのか?といった、
世界遺産という物の概念を扱った分野です。
基本的な重要キーワードを解説!
重要な言葉やポイントについて解説していきます。
顕著な普遍的価値
「Outstanding Universal
Value=顕著な普遍的価値」
簡単に言うと世界中の誰しもにとって価値のあるもの(遺産)ということです。ある特定の地域の人だけやある特定の宗教にのみ価値があるものであってはいけないのです。
この言葉の意味、パッと見は良くわかりませんし、よく考えてもわかりません。なぜかというと、英語で考えられた概念を無理やり日本語に訳したからです。
しかし、この「顕著な普遍的価値」という言葉は
世界遺産を考える上では絶対にはずせない言葉です。なぜなら、この概念が備わった遺産しか
世界遺産に登録されないからです。
試験に出題されるされない以前に、
世界遺産を学習する人なら絶対に知っておきたい言葉です。この言葉を絡めた問題はしばしば出題されます。
ICCROM(イクロム) :
文化遺産の
保全状況の監督を行う。
ICCROM(イクロム) : 文化遺産の保全状況の監督を行う。
IUCN (アイユーシーエヌ): 自然遺産の登録可否を行う上での専門的調査や審査を行う。
世界遺産条約締約国(
世界遺産の概念に賛同する国、約190ヶ国)のうち持ち回りで21ヶ国が委員国となって、年に一度以上
世界遺産委員会を開催し、新たな遺産の登録可否や既存の遺産の
保全状況等について協議します。
その協議をする上で3つの諮問機関(審査機関)の役割を理解する。
ⅰ~ⅵは
文化遺産、ⅶ~ⅹは自然遺産。両方の基準を備えるものを
複合遺産と言います。
この登録基準の番号と内容は頻出ですので、上にあげるようなキーワードだけでも良いので覚えるようにしましょう。
文化遺産は6つあるのですが、何番の登録基準がどんな内容であったか覚えられないという人もいるので、私なりの覚え方をご紹介します。ⅰ→ⅵの順番に覚えます。
ⅰ人間の才能で建物が建築されると、ⅱ人々が行き交い、文化の交流がなされ、ⅲそこには文明があったことが証明され、ⅳその後、新たな建築技法により町の建設がなされ、ⅴ独自の集落が誕生すると、ⅵそのこと自体が大きなできごとになった。
やや強引なところは置いといて、順序立てて覚えてください。
文化的景観
総論の中でこの概念は非常に理解しにくいものの一つです。
セオリーで書くと「人間社会が自然環境に影響を受けながら進化してきた遺産」となるのですが、ほとんど意味が分かりません。
具体的な物件を見ながら理解しましょう。
文化的景観の話をする時に必ずと言っていいほど出てくる物件が「トン
ガリロ国立公園」です。世界で初めて文化的景観が認められた物件でもあります。
トンガリロ山をはじめとした美しい自然の景観に影響をうけながら、先住民のマオリ族が営む文化も同時に息づいてきた、それらを総合したところに遺産としての価値があるというわけです。
美しい景観のもとにその地の独自文化が成り立ってきたという遺産に文化的景観という考えが認められるのです。
国境線にとらわれることなく、2国間以上にまたがって存在する遺産。
また、2016年に
世界遺産登録されたル・コルビジュエの建築作品はその遺産がフランスやインド、アルゼンチン等大陸をもまたいで1つの
世界遺産として登録されており、初めてのトランスコンチネンタル・サイト(大陸をまたいだ遺産)となりました。
シリアル・ノミネーションサイト
個々の遺産の立地は一定の距離離れているが、登録されることとなった一連のストーリーの中で選ばれた複数の遺産や同種の資産、生態系をまとめて一つの
世界遺産として登録しているもの
具体的には、2015年に登録された明治の日本の
産業革命遺産は、一連の明治期の
産業革命で活躍した製鉄所や造船所、鋳造所等を
世界遺産に指定していますが、遺産が存在する場所は
長崎県や
山口県、
静岡県等に散らばっています。立地が離れていても一つの一連の遺産として登録されたものをシリアル・ノミネーションサイトという。
かつては
世界遺産に登録される遺産は中世から19世紀にかけての欧州の宮殿や教会、城等に偏っていたことを受け、それら以外の遺産についても
世界遺産としての価値を見出して積極的に登録していくという戦略。
・産業、鉱山、鉄道関係の強化(フォース橋、など)
・先史時代の遺跡強化(アルタミラの壁画、など)
他にも総論には頻出の概念はありますが、特に重要なものやテキストを一見しただけでは理解が難しいものについてピックアップしました。
最後にまとめておきたいのが、上でご紹介した文化的景観のような様々な概念が発出された歴史を覚えておく必要があります。
世界遺産に関する重要年表です。
1931年 アテネ憲章
1945年 ユネスコ設立
1948年 IUCN設立
1956年 ハーグ条約
1956年 ICCROM設立
1964年 ヴェネチア憲章
1965年 ICCOMOS設立
1971年 MBA計画
1972年 人間環境宣言
1972年 世界遺産条約採択
1977年 第1回世界遺産委員会開催
1978年 最初の世界遺産12件が世界遺産リストに記載
1992年 日本が世界遺産条約を批准
1992年 文化的景観の概念が採択
1993年 屋久島、姫路城、白神山地、法隆寺地域の仏教建築物群が日本初めての世界
遺産として登録。
1994年 グローバル・ストラテジーの概念が採択
1994年 奈良文書採択
2014年 オカバンゴデルタが1000件目の世界遺産として登録
2015年 明治日本の産業革命遺産が日本初のシリアルノミネーション・サイトとなる
現在の世界遺産の保全につながる重要な出来事を並べた年表です。出来事の順番とと共に年号もできるだけ覚えましょう。
まとめ
今回ご紹介したのは世界遺産検定の中で配点の25%程度を占める、世界遺産の総論について解説しました。
上に挙げたキーワードは重要ですが、テキストを丸暗記するのではなく、なぜそのような概念、考え方が生まれたのか、その背景をしっかり理解した上で覚えていってくだい。
具体的な遺産とリンクさせて覚えるのも、尚良いでしょう。
今回のこの記事だけ読んでいただいて、総論の試験対策とすることは難しです。(これだけで完全に理解していただこうと思って書いていません)
公式テキストでは堅っ苦しい表現でなかなか理解するのが難しい、と思われる点をピックアップしましたので、是非公式テキストを読み進めながら、参考書的に使ってみてください!
いつもご覧いただきありがとうございます。
これからも応援していただけると励みになります。
★のクリックお願いします!

にほんブログ村
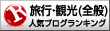
全般ランキング